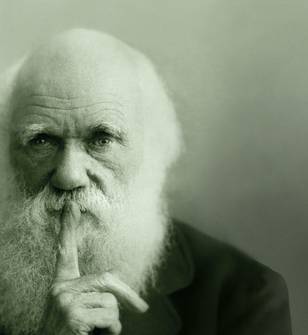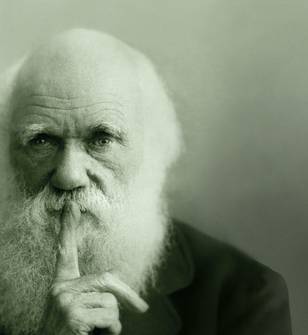< ダーウィンと神 >
〜 宗教上の信仰 〜
この二年間、わたしは宗教についてたくさんのことを考えされられた。ビーグル号に乗船中、私は全く正統派だった。私は、道徳上のある問題にかんし反論不能の権威として聖書を引用したことで、数人の士官(かれら自身も正統派であったのに)に思う存分笑われたことをおぼえている。かれらをおもしろがらせたのは、私の議論がもの珍しいものであったためだろうと思う。しかし私はそのころ徐々に、旧約聖書が、バベルの塔とか”しるし”としての虹とかのようなものを含む明白に誤りの世界史であることから、また復讐心の強い暴君の感情を神に帰していることから、ヒンズー教徒の聖典や未開人の信心以上には信じられないものであると見るようになっていった。疑問はそれからのち絶えず意識にのぼり、追いはらうことができなかった。・・・もし神がいまヒンズー教徒に啓示をあたえるとしたら神は、キリスト教が旧約聖書と和合しているように、その啓示がヴィシュヌ、シヴァなどへの信仰と結合されることを許すと信じられるだろうか。そんなことは全く信じられないように私には思われた。
さらに、つぎのいろいろのことをいっそうよく考えることによって、すなわち、キリスト教を支えている奇跡を健全な精神の持主に信じこませるにははっきりした証拠が必要であるということ、・・・確定された自然の諸法則を知れば知るほど、奇跡はますます信じられなくなるということ、・・・その当時の人間はわれわれには理解しがたいほど無知で信じやすかったということ、・・・福音書はいろいろの事件と同時期に書かれたとは証明できないということ、・・・それらの事件は多くの重要な細部に違いがあり、それは目撃者にありがちな不正確者として許されるにはあまりにも重大でありすぎるということ、・・・わずかでも新しさや価値があるというためではなく、私に影響を与えたという理由でここにかかげた、これらいろいろの考えによって、私は徐々に神の啓示としてのキリスト教を信じなくなった。多くのまやかし宗教が野火のように地球上の大きな部分に広がったという事実は、私にとってかなり重大であった。新約聖書の道徳性は美しいけれども、その完全さは部分的には、いまわれわれが隠喩や寓言にあたえている解釈しだいだということは、否定しがたいのである。
しかし私にとって、自分の信仰を放棄するのはとても不本意のことであった。・・・私は、確かにそうであったと思う。なぜなら私は、ポンペイその他の地で著名なローマ人たちのあいだにとりかわされた古い手紙や写本が発見されて、福音書に書かれているすべてのことをまったくみごとに確証するといった夢物語を、何度も何度もつくりあげたことを、よく記憶しているからである。しかし私は、空想を自由に働かせても私を確信させるにたりる証拠を発明することがますますむずかしくなるのを知った。こうして不信心は非常にゆっくりした速さで私にしのびよってきたが、最後には完全になった。その速さはまったくゆっくりであったので、私は苦痛を感じなかったし、また私はその後一秒たりとも自分の結論が正しいことを疑ったことはなかった。実際、私には、なぜ人はキリスト教が真理であることを希うのか、理解しがたい。というのは、もしそうであるなら、聖書のことばを文字通りにとれば、不信心の人たちは永遠に罰せられることになり、それには私の父、兄、ほとんど全部の最良の友人たちが含まれることになるからである。
そんなものは、いまいましい教理だ。
私は、人格神の存在については、私の人生のかなり後の時期まで考えたことがなかったが、私の到達させられたぼんやりした結論をここに述べておきたい。ペイリーが与えているような、自然の計画についての古い議論は、以前には決定的なもののように私には思われたが、自然選択の法則が発見されたので、もうだめである。われわれはもはや、たとえば2枚貝の美しい蝶番が、ドアの蝶番が人間によって作られるのと同様に、ある知的な存在によって作られたに違いないという風に論じることはできない。生物の変異性の中には、また、自然選択の作用の中には、風がどんな道を通っていくかという場合以上に、計画など存在しないように思われる。自然界のすべてのものは、確定された諸法則の結果である。しかし、私はこの問題を著作『家畜および栽培植物の変異』の最後で論じておいた。私がそこでした議論は、私の知る限り反論されていない。
しかしわれわれがどこででも出会う際限のない美しい適応を見ないでおいたとしても、世界が一般に慈悲深い配置になっているのはどう説明したらよいのかと、問われるかもしれない。ある著者たちは、世界の苦痛の総量に強く印象づけられていて、それでその人たちは、われわれが知覚をもつ生物の全部を見わたしたとき、そこには悲惨のほうが多いか幸福の方が多いか、・・・世界は全体としてよいものなのか悪いものなのかを、疑問とする。私の判断するところでは、幸福が決定的に優越している。もっとも、これを証明するのはむずかしい。もし、この結論の真実性が認められるならば、それはわれわれが自然選択から期待しうる効果とよく調和する。どの種の個体もすべて、極度に苦しまねばならないのが普通だとしたら、それらの個体はおのれの種類をふやすことなど怠ってしまうであろう。しかし、こうしたことがかつて、あついは少なくともたびたび起ってきたと信ずべき理由はない。若干の他の考察は、さらに、知覚をもつすべての生物は、一般的な規則としては、幸福をたのしむようにつくられてきたという信念に到達させる。
すべての生物の、すべての身体的および心的器官(その所有者にとって有利でも不利でもないようなものは除けば)は、自然選択すなわち最適者生存と、また使用あるいは習性によって発達してきたものであると、私と同様に信ずる人はだれでも、これらの器官は、その所有者が他の生物との競争に成功し、それにより個体数を増やすようにつくられてきたということを認めるであろう。さて、動物は、痛み、飢え、乾き、恐れというような苦しみによって、・・・あるいは食べることや飲むこと、種を広げること、その他の喜びによって、あるいは食物を探す場合のように双方が結合したところのものによって、その種にとってもっとも有利な活動の道を進むようにされるであろう。しかし、どんな種類のものにしろ、苦痛あるいは苦脳は、長くつづけば衰弱を起させ、活動力を弱める。ところがそれは、生物がどんな大きな、また突然の災害にたいしても自分の身を守れるようにするために、よく適応したものになっている。他方、快感は、衰退させる作用作用なしに長くつづくことができる。それどころか反対に、それは、系全体を、活動を高めるように刺激する。だからほとんどの、あるいはすべての、知覚をもった生物は、自然選択によって、快感が習性的な道案内の役をするように発達してきたわけなのである。こうしたことは、活動したことによってえられた喜び、ときには心身を大いに働かせたことによって喜びがえられることで知ることができる。・・・またそれは、日々の食事の喜びや、ことに社交および家族を愛することによる喜びのなかに見られる。これらの喜びには習性的なものもあり、頻繁に反復されるものもあるが、それら喜びの総量は、大多数の知覚をもつ存在にたいして、ときに苦痛を受けるものも多くあるにしろ、悲惨より幸福をずっと多く与えているということを、私はほとんど疑いえない。いまいった苦痛も、自然選択への信念と矛盾するものではない。自然選択の作用は、完全なものではない。そうではなくて、それはただおのおのの種を他の種との、おどろくべき複雑でまた変化しつつある環境のもとでおこなわれる生存のためのたたかいにおいて、できるだけの成功をおさめるようにさせるにすぎないのである。
世界に多くの苦痛があるということは、だれでも認める。ある人たちはこのことを、人間にかんしてだが、それはモラルの改善に役立つというふうに想像して説明しようと試みた。しかし、世界中の人間の数は、他のすべての知覚的生物の数と比較すればなにほどのものでもなく、そしてこれらの生物はしばしば、モラルの改善はなしにいちじるしく苦痛を受けているのである。全世界を創造することが出来た、神のような力と知識にみちた存在は、われわれの限られた知力にたいしては、全智全能であるわけだが、その神の慈悲が無限でないと仮定することはわれわれの理解に反する。というのは、ほとんど無限の時間をつうじて無数の下等動物が苦痛を受けるということに、どんな利益もありえないからである。苦痛の存在は聡明な第一原因の存在に反するというこの非常に古い議論は、強い力をもつもののように私は思われた。だがしかし、いま上に述べたように、多くの苦痛が存在することは、全生物が変異と自然選択によって発達してきたとする見解によく合致する。
今日では、聡明な神の存在を証明する最も普通の論拠は、ほとんどの人が経験する深奥の内的な信念および感情からひきだされている。しかし、ヒンズー教徒や回教徒その他も同じようにして、また同等の力をもって、唯一神あるいは多数神の存在を説くであろうし、また仏教のように神の存在を否定するであろうことは、疑いえない。われわれが神と呼ぶようなものを信じているとはどうしてもいえないような未開な種族もある。それらの種族は実際に精霊や幽霊を信じており、タイラーやハーバード・スペンサーが示したように、このような信仰がどうして生じたかを説明することができる。
以前に私は、いま言ったような感情によって(宗教的な心情がかつて私のなかに強力に発達したことがあったとは思わないが)、神の存在と霊魂の不滅とにかんする確固たる信念に導かれた。私は航海記のなかに、ブラジルの森林の荘厳のただなかに立っているあいだ、「私の心をいっぱいにし高揚させる驚異と讃嘆との気高い感情を適切にあらわすことができない」と書いた。人間には、単なる肉体の呼吸以上のものがあると堅く信じたことを、私ははっきりおぼえている。しかし現在では、その荘厳きわまりない光景も、私の心にこのような信念や感情をよびおこさせるものとはならないであろう。実際、私は色盲になった人間のようなものであり、そして、だれもかれもが赤い色の存在を信じているために、私の現在の知覚喪失は、証拠としてまったく価値がないものにされてしまっているといえるかもしれない。この議論は、もし、すべての種族のすべての人間が唯一の神の存在について同一の内的な信念をもっているのであったら、妥当なものとなるであろう。ところが、実際はまったくそうでないということを、われわれは知っているのである。だから、私は、このような内的な信念や感情が真に存在するものの証拠としていくばくかの重みをもつものであるとは考えられない。壮大な光景が以前に私にひきおこし、そして神への信仰と緊密に結びついていた私の心の状態は、よく崇高の感情と呼ばれるものと、基本的には違っていなかった。この感情の発生を説明することは困難であろうけれども、音楽によって起される漠然としてはいるが力強い、またはそれに似た感情と同様に、それを神の存在の論証としてもちだすことはむずかしい。
不滅性にかんしては、それがいかに強力でまたほとんど本能的な信仰であるかを示すものはなにもない。現在大多数の物理学者が採用している見解、すなわち太陽とその全惑星とは、実際に何か大きな物体が太陽に突入してそれに新たな生命を付与するのでなければ、時がたつにつれて冷却し生命が存在しえなくなる、ということについて考えてみればよい。・・・人間は遠い未来において現在よりはるかに完全なものになろうと私は信じており、もしそう信じるならば、人間およびその他の全知覚生物が、このように長くつづいたゆっくりした進歩の後に完全に絶滅すると宣告されているということを考えるのは、耐えがたいことである。人間の霊魂の不滅を完全にみとめる人々にとっては、われわれの世界の崩壊はそれほど恐ろしくは思われないであろう。
神の存在への信念のもう一つの源泉は、感情にではなく理性に結びついたものだが、それは、もっとずっと重みをもつもののように、私は印象づけられている。これは、遠い過去やはるかな未来までも見る能力をもつ人間を含めて、この広大で不思議な宇宙を盲目的な偶然や必然の結果として考えるのが極度に困難である、むしろ不可能であるということからの結論である。このように考えたときには、人間とある程度似た知性的な心をもった第一原因に目を向けることを余儀なくされるように感じる。この場合、私は有神論者と呼ばれてもよい。
この結論は、思いだせる限りでは、私が『種の起原』を書いたころ、私の心のなかに強くあった。そしてそれ以後に、たびたび強くなったり弱くなったりしながらだが、きわめて徐々に弱まっていった。しかしそこで疑問が生じる。・・・人間の心は最下等の動物がもっていたずっと低度の心から発達してきたものだと私は完全に信じているが、そのような人間の心を、それがこのように偉大な結論をひきだせるものだと、信用してよいのであろうか。これらは、必然的なものとしてわれわれに感じられる原因と結果の間の結合の結果なのではなくて、おそらく単に、遺伝された経験によるものにすぎないのではないか。またわれわれは、子どもたちの心に神への信仰をいつもいつも教え込み、子どもたちのまだ十分に発達していない頭に非常に強い、そしておそらくは遺伝される影響を生じさせ、それで子どもたちが、サルがヘビへの本能的な恐怖と憎悪を捨て去れないのと同様、神への信仰を捨てるのが困難になるということがありうることも、見逃してはならない。
私は、このような深遠な問題に少しでも光を投じえたかのようによそおうことはできない。あらゆる事物のはじめという神秘は、われわれには解きえない。私個人として不可知論者にとどまらざるをえない。
人格神の存在、あるいは応報のある来世の存在を、確固としてまた永続的に信じているのではない人は、私がみるかぎりでは、その生活の規則として、ただもっとも強い、あるいはその人にとってもっとよいものに思える衝動や本能に従うことだけしかできない。犬はこのように行動するが、それは盲目的なものである。他方、人間は、前後を見、自分のいろいろな感情、欲求や記憶を比較する。そうすると、もっとも賢明な人びとの判断と一致して、もっとも高度の満足はきまったいくつかの衝動すなわち社会的な諸本能からえられるということが、知らされる。もし人が他人のためになるような行為をすれば、その人は仲間からほめられ、ともに生活している人たちから愛される。このように愛されることは、疑いなく、この世で最高の喜びである。人はしだいに、自分の高尚な衝動をこえて感覚的な激情に従ってしまうことがどうしても我慢できないようになる。そしてその高尚な衝動が習慣的になると、それはほとんど本能と呼んでよいものになる。かれの理性は、ときおり、他人の意見に反対して行動するようにかれに命ずる。他の人々の賞賛は、そのときには受けられない。しかしそれでもかれは自分の内奥の導き、すなわち良心に従ったということを知って真の満足をうるのであろう。・・・私自身について言えば、私は終始変わりなく科学に従事し自分の生涯をそれに捧げるという点で、まちがいなく行動してきたと信じている。私は、なにか大きな罪を犯したということで悔恨を感じてはいないが、しかし同胞にもっと多く直接の善行をしなかったということを遺憾に思ってきた。私にできる唯一の貧しい弁解は、自分が非常に病身であるということと、私の心の構造が一つの問題から他のものに転換するのを非常にむずかしくさせるようなものだということである。私は自分に時間の一部ではなく全部を慈善のためにあてることを空想してたいへん満足することができる。そのほうがずっとよい生き方であったかもしれないのだが。
私の後半生でなによりもいちじるしいのは、懐疑主義、あついは合理主義がひろがっていったことである。私は婚約するようになる前に、父は私に、自分の懐疑は用心深く隠しておくようにと忠告した。こうしたことで起った極度の不幸を自分は知っていると、父は言ったのである。妻はまた夫が健康でいるあいだはうまくいっていたのだが、病気になると、ある婦人たちは夫(の魂・・・訳者)が救済されるかどうかを疑ってみじめに苦しみ、夫のほうも苦しむようになってしまった。父はそれにつけ加えて、自分の長い一生のあいだにたった三人だけ、懐疑家であった婦人を知っていたと言った。父は非常に多くの人々をよく知っており、しかも信頼をかちえる非凡な力をもっていたということを、思いだしてもらいたい。その三人の婦人というのはだれだったのですかと私がたずねたとき、父は、その一人である自分の義妹キティ・ウェジウッドにかんしては、じつは十分な証拠はなく、ただきわめて漠然としたヒントだけであり、非常に明敏な婦人は信仰者でありえないという自分の信念が加わっているのだということを、みとめねばならなかった。現在では私は、私の数少ない知人のなかでも、夫よりもずっと信仰の薄い既婚女性を幾人も知っている(あるいは知っていた)。父はいつも反論ができない論拠を引きあいにだしたものだった。それで、父が異端なのではないかと疑っていたバーロウ夫人という老婦人が父に回心をねがってつぎのように言った。「先生。私はお砂糖を口にいれると甘いことがわかります。私には救世主さまが生きておいでのことがわかります」
(「ダーウィン自伝」より)
< 神への信仰 >
人間がもともと、全能の神の存在を信ずる高尚な信仰を与えられていたという証拠はない。それどころか、唯一神の、あるいは多くの神々の観念をもたず、自分たちのことばにもそのような観念を表現する語をもたない人種が非常にたくさんあったし、そのような人種は現在でも存在するということの証拠が、そのあたりを素通りの旅行をしてきた人からではなくて、長いあいだ未開人と生活をともにしてきた人からたくさんもたらされている。この問題はもちろん、宇宙の創造者であり、かつ支配者なるものがいるかどうかというような、もっと高遠な命題とは全く別な問題であり、そういう存在は、かつてこの世に生をうけた最も知性のある人たちによって肯定されてきたのである。
しかし、もしわれわれが「宗教」という語に、目に見えない、または心霊的な力に対する信仰を含めるならば、事情は全く異なってくる。というのは、こういう信仰はあまり文明的ではない人種に普遍的であるらしいからである。さらに、それがどのようにして起こったかを理解するのもむずかしいことではない。想像、驚異、好奇心、それになんらかの推理力も合わせて、こういった重要な能力が発達するやいなや、人間は当然自分の身のまわりにおこった物事を理解したいと望むだろうし、自分自身の存在について、ぼんやりとでも考えたことであろう。
マックレナン氏がいったように、「人間は生命現象についてのなんらかの説明を、みずからつくりださなければならなかったであろう。そして、その説明の普遍性から判断して、人間が最初に考えた最も簡単な仮説は、人間が自分たち自身がもっていると意識しているような、行動に駆りたてる霊が、動物にも、植物にも、無機物にも、さらに自然力にも存在し、自然現象はこの霊の存在にもとづくのだ、ということであったように思われる」
タイラー氏が示したように、夢が最初に霊の概念を生んだのかもしれない。というのは、未開人は主観的な印象と、客観的な印象とを、容易には区別できないからである。未開人が夢を見ると、彼の前に現われた像は、どこか遠いところからやってきて、彼の上に立つのだと信じられる。または、「夢をみている人の魂が旅に出て、みたものを記憶して帰ってくる」と信じるのである。しかし、創造力、好奇心、理性などの能力が心のなかでかなりよく発達するまでは、人間はイヌの場合と同様に、夢によって霊を信ずるまでにはならなかったであろう。
未開人が、自然物や自然力は、霊的もしくは生命ある実体によって生気づけられているのだと想像する傾向は、たぶん、私がかつて注目したちょっとした事実によって説明できるであろう。私が飼っていたイヌは、完全に成長しており、非常に感覚の鋭いイヌであった。ある暑い静かな昼、このイヌが芝生の上にねころんでいた。少し離れたところにパラソルが開いたまま置いてあった。ときおり、そよ風がそれを動かした。もしだれかがそのそばに立っていたなら、イヌはパラソルなどは完全に無視しただろう。しかし、だれもいなかったので、パラソルがわずかに動くたびに、このイヌは激しくうなり、そしてまた吠えた。彼は自分で、はっきりとした原因もなしに動くのは、なにか不思議な生きた力があるということや、また、よそものには自分のなわばりの中に侵入する権利はないのだぞと、とっさに無意識的に思ったのだと私は考える。
心霊的な力を信ずることは、すぐさま唯一神、あるいは多くの神々の存在の信仰へと進むであろう。というのは、未開人は当然、霊もまた、彼ら自身が感じるのと同じ情熱をもち、そして彼らと同じような愛情をもっていると考えているからである。フェゴ島の原住民は、こういう点では中間的な状態にあるらしい。というのは、ビーグル号の軍医が、標本にするために数羽のカモの子を撃ったとき、ヨーク・ミンスターという男が、いとも荘重に、「おお、ビノーさん、大雨、大雪、大風になりますよ」と宣言した。これは明らかに、人間の食物を浪費したことに対する因果応報の罰をいっているのであった。しかし、われわれはフェゴ島の原住民がわれわれが神と呼んでいるものを信じているか、あるいは宗教的な儀式をおこなうかどうか、ということは全くわからなかった。
宗教的な信心の感情というものは、非常に複雑なものである。そしてそれは、愛、高貴で神秘的で卓越した人への完全な服従、強い依存の感情、懼れ、尊厳、感謝、未来への願望、その他おそらくもっとほかのいろいろの要素によって構成されている。いかなる生物も、その知的かつ道徳的な能力が、少なくともかなり高い段階にまで発達しなければ、このような複雑な感情を経験することはできないのである。
しかし、イヌの主人への深い愛には、かすかながら精神のこの段階への近づきをみることができる。これには、完全な服従、ある種の懼れ、そしてたぶん、そのほかの感情も伴っている。長く会わなかったあとで主人のところに帰ってきたイヌの行動や、最愛の飼い主に対するサルの行動もつけ加えてよいと思うが、これらは自分の仲間に対する行動とは非常に異なっているのである。自分の仲間に対する場合には、喜びの絶頂といった感情は、それほどあらわれず、あらゆる動作に平等感といったものがあらわれる。ブラウバッハ教授は、イヌは神をみるように自分の主人を見ているとまでいっている。
高度な心理的能力は最初に人間を、目に見えない霊の力を信ずるように導き、それから諸仏崇拝に、そして多神教に、最後には一神教を信ずるように導いたが、それと同じ能力が、人間の理性の力があまり発達しない状態にとどまる場合では、いろいろな奇妙な迷信や、風習に導いたということは疑いないことである。
しかし、ときにはこれらの迷信について考えるのもよい。というのは、それらはわれわれがどれほど多くのことを、理性の発達に、科学に、蓄積された知識に負っているかを、大いに感謝すべきであるかということがわかるからである。ラボック卿がうまくいっている。「未知の災害に対するひどい恐怖は、厚い雲のように、未開人の生活の上に垂れこめ、すべての楽しみをみじめにするといっても過言ではない」
< 人間の先祖 >
人間は、人間の水準に達してから後に、いろいろの人種、もっとぴったりした呼び方でいうならば、亜種に分かれたのである。ニグロとヨーロッパ人を比べるとわかるように、人種同士で著しく異なるものがあるから、なんの説明もつけないで、その標本を博物学者のところに持ちこんだら、博物学者はそれらの標本をきっとりっぱな本ものの種だと考えるにちがいない。しかし、どの人種においても、体のあまり重要でない細かい点や、また多くの心理上の特性においてよく一致するものであるが、これらの一致は、すべての人種が共通の先祖から、そういう形質を遺伝によって受けついだのだという以外に説明のしようがないのである。そして、こういう形質をもった先祖こそ、おそらく人間の列に加えることができるものであろう。
人種間の違いや、世界じゅうの人種をある一つの人種と比べてみてどの程度に異なっているかということを調べ追求しても、あらゆる人種が結局はある一種の先祖から分かれたというところまで遡ることができようとは思えない。逆に、変化の過程のどの段階においても、程度の差こそあれ、その生活条件になにかの面でより適した個体は、どんな個体でも、あまり適さなかった個体よりも数多く生き残ったと考えられるのである。その過程というのは、人間が家畜を扱う場合、特定の個体をことさら選ぶわけではないけれども、すべてのすぐれた個体の子をふやし、劣った個体を軽んじる、その過程と似ていただろう。人間はこのようにして、種族を、遅々とした歩みではあるが着実に変化させ、知らず知らずのうちに新しい種族をつくりあげるのである。
淘汰とは、関係なく獲得された変容で、その生物の性質や環境条件からおこる変異とか、生活習性の変化によって生じる変異が原因となっている変容も、やはり同じであって、ある一組のものが同じ地域に住む他の組のものよりいっそう強く変化することはなかったであろう。なぜならば、すべてのものが自由に交雑しあい、絶えず混ぜ合わされたはずだからである。
人間の胎生期の構造、人間と動物とにみられる相同機関、人間のもっている痕跡器官、人間におこりがちな先祖返りなどを考慮すれば、われわれの初期の先祖たちがかつてどんな状態だったかを、いくぶんかは想像することができ、またその先祖たちを動物学的な系統の中でほぼ正しい位置に据えることができる。このようにしてわれわれは、人間は毛深く、尾があり、おそらく樹上性の四足獣で、しかも旧世界に住んでいたものから派生したことを知るのである。この動物の構造を、もしも博物学者がくまなく調べたならば、それはこれよりさらに古い旧世界ザル類や新世界ザル類の先祖が確かにそうであるように、サル類の一員として分類されるに違いない。
サル類、その他すべての高等哺乳類は、おそらく古代の有袋類の一種から分化し、その有袋類は両生類に似たあるいは動物から分かれ、長い間いろいろな形態を次々と経たのちに生じたものであり、さらにその両生類に似たものは、魚に似たある動物に由来するものである。ほの暗い過去の闇の中にわれわれが認めることができるのは、あらゆる脊椎動物のいちばん古い先祖は水棲動物であって、それは鰓をもち、雌雄同体で、脳とか心臓のような体の最も重要な器官はまだ不完全だったか、それとも全く形成されていなかったのだということである。この動物は、今までわかっている生物のなかでは、海にいる現生のホヤ類の幼生にいちばんよく似ていたと思われる。
< 愛と良心 >
道徳的資質の発達の問題は、もっと興味深い。その基礎は社会的本能のなかにあるが、この社会的本能ということばには、家族の絆という意味も含まれている。この本能は複雑きわまりないもので、動物の場合には、ある一定の行動をするような特別の方向づけを与えるものである。しかしこの本能の重要な要素は、愛であり、同情というまた別の感情なのである。社会的本能を賦与されている動物は、互いに仲間になることを喜び、仲間同士で危険を知らせあい、いろいろなやり方で守りあい助けあう。こういう本能は、その種の全個体にへだてなく発揮されるものではなく、同じ共同体に属している個体だけに及ぼされる。この本能は、その種にとっては非常に有益なものだから、自然淘汰によって獲得されたとみて、十中八九まちがいない。
道徳的な存在とは、自分の過去の行為そのものとその動機を反省し、あることを是とし、あることを非とすることのできるものである。そして人間は確かにこの名に値するものだという事実こそ、人間と動物を区別するあらゆる差異のなかの最たるものである。しかし、私は第四章で、道徳的感覚というものは、第一には、社会的本能の性質というものが長く持続し常に存在するものであること、第二に、人間は仲間の賞賛や非難を感じとるものであること、第三に、人間の心理的能力は非常に活発で過去の印象を鮮やかに蘇らせることができること、当然以上の三点からおこったことを明らかにしようと努めた。この三つの最後の点で、人間は動物とは違うのである。
人間はこのような精神的な状態になったために、将来にも過去にも目を向け、過去のいくつかの印象を互いに比較するのを避けることができなくなった。そこで、人間の社会的本能が、ある一時的な欲望や情熱に抑制されるようなことがあると、人間はあとになって、いまや弱められているそういった衝動にもとづいた過去の印象を反省し、それを常に存在する社会的本能と比べてみる。そして、どんな本能でも満たされないとき、いつもあとに残る不満足を味わって、今度はそれと同じ行為はすまいと決心する。これが良心なのである。
他のような本能よりも、常に強くかつ長続きする本能は、われわれが、したがわなければならないと、ことばにだして言い表わしている感情をおこさせるのである。ポインターが、もし自分の過去の行ないを反省することができるならば、そのイヌは、私はあそこにウサギがいることを示すべきであって、それを追いかけたいという一時的な誘惑に負けるべきではなかった、と自分にいいきかせるだろう。
社会的な動物というものは、自分の共同体の仲間をただなんでもないやり方で援助したいという欲求に駆られることもあるが、ある特定の行動をしたいという欲求に、もっと強く動かされるのである。人間も同じように、自分の仲間を助けたいという一般的な欲求に駆られるのだが、そのための特別な本能などというものはほとんど、あるいは全くもっていないのである。人間は自分の欲望をことばで表わす能力があるという点で、動物とは違っているが、ことばがこのように助けを求めたり与えたりするときの手がかりになるのである。
他人に力をかそうとする動機も、人間では非常に違ってきている。それはもはやたんなる盲目的な本能的衝動というものではなく、仲間の賞賛や非難というものと大いに関係がある。人から誉められたりけなされたりすることをよく悟り、また人を誉めたりけなされたりするのは、ともに同情という感情があるからである。そしてこの感情は、すでに述べたように、社会的本能の重要な要素の一つである。同情という感情は、一つの本能として獲得されたものではあるが、やはりそれをよく使い、習性とすることによって強めることができるものである。
自分の幸福を願わぬものはないから、いろいろな行為や動機に対して与えられる賞賛とか非難は、それがこの幸福という目的にどうつながるかによって決まる。そしてこの幸福というものは、全体の福祉にとっても正邪を決めるほぼ信用に足る基準として、間接的に役だつものである。推理する能力が発達し、経験が豊かになるにつれて、ある一連の行為が個人の性質や全体の福祉にどういう効果を将来与えるかということを感知できるようになる。そうなると、自重の徳というものが世論のなかにはいってきて、それが賞賛を受け、それと反対のことは非難されるのである。ところが文化水準があまり高くない国民では、理性がよく誤った方向にはたらき、いろいろの悪習や下劣な迷信が同じく世論に組みこまれるようになり、それがりっぱな美徳と認められ、それに違反することは大罪とみなされることがある。
道徳的な能力は一般に知的能力より重くみられているが、これは正しいことだ。しかし、われわれは過去の印象を生き生きと呼びおこす心の活動が、二次的ではあれ、良心の根本的な基礎の一つであることを心にとめておくべきである。これがあらゆる人間の知能をありとあらゆる方法を使って教育し、叱咤激励しようとするときの最も強力な論拠となるのである。愚鈍な人でも、もし社会的な愛と同情という感情がよく発達しているならば、よい行いをするようになり、またかなり鋭い良心をもつことができるようになり、疑問の余地がない。しかし、想像力をより活発にさせ、過去の印象を思いおこして比べる習慣を強めるものは、それが何であろうと、良心をもっと鋭くするであろうし、社会的な愛と同情が弱くても、その埋め合わせをいくらかでもするであろう。
人間の道徳的資質が現在の標準にまで達したのは、一つには人間の理性が発達して正しい世論を喚起したからであるが、一つには、習慣や、規範や、教育や、反省などのおかげで、同情という感情がもっとやさしくなり、かつ広く普及したからであって、このほうが主要な原因なのである。美徳というものは、これを長期間にわたっておこなえば、遺伝することもありえないことではない。
かなり文明の進んでいる人種では、すべてを見通す神が存在するという確信が、道徳の向上に多大の影響を及ぼした。人間は仲間の賞賛や非難を気にして、それで自分の行為が左右されることを免れることはできないが、ついにはそれを唯一の指針とは受けとらなくなり、習慣的になった確信が理性に支配され、それが自分の最も安全な標準となる。そこで、自分の良心が最高の裁判官となり助言者ともなる。それにもかかわらず、道徳的意識の最初の基礎、つまり起原となるものは、同情という感情をも含めた社会的本能のなかに見いだされる。そして、この本能は最初は動物の場合と同じように、自然淘汰によって得られたことは確実である。
(「人間の起原」より)